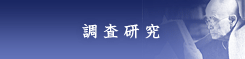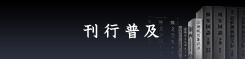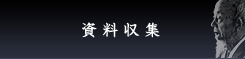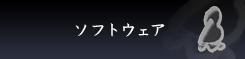脳死問題研究会 研究報告
研究討議の推移概要研究会は、先ず、1)「脳死および臓器移植」ということで問題となっている事柄を出来るかぎり広範囲に 且つ正確に把握すること(脳死問題に関する主だった情報の収集)と、2)この問題に対する各界の意見を整理し検討すること(情報の分析と整理)から始まった(第1および2回研究会)。諸情報は、後藤典生氏(臨済宗連合各派布教師会事務局長)の尽力により、医学界(日本医師会や各大学病院など)に設けられた各種懇談会および倫理委員会の内部資料から、他学界(日本印度仏教学界)が公表した見解および各種の新聞雑誌に掲載された個人の意見にいたるまで、主だったものが集められ、検討された。 検討の結果、討議すべきテーマとして、
討議の中心となった事柄は、社会の論議においてと同じように、整理すればほぼ以下の如き諸事項であった。
〈大峰先生〉のご意見は「脳死を人間の死と定義しなければならない。そうすることによって初めて、人間の生命の尊厳、人間の尊厳に本当に応え得る」というものであった。先生は、「初めに移植ありというような見方をされている人があります。そうではなくて、初めに脳死があったのです」と言われ、脳死というものが、患者の生命を救おうとする「医の原点」・「医の倫理」から、現在の「先端医療現場に生まれた新しい事象」・「やっかいな新しい現象」であり、「人類が今の文明段階で背負い込んだ業のようなもの」であると言われた。しかし、今重要なことは、この脳死の事実、すなわち、人体における「反射統合作用が、一時的にではなく、不可逆的(正常な作用力を回復することなく)に停止する」という事実を、我々が直視することであると説かれた。 脳というものは、他の諸臓器と異なり、身体を統合している器官であり、人の意識ないし心の宿る場所(「精神が物質にはめこまれる場所」)、すなわち、単に物質とか分量というものに還元できない質をになった場所である。人の尊厳というのは、生命が物質に還元できないそういう質というものをその核心に有しているということの自覚にある。その質をになっている脳が不可逆的にその機能を停止したことが医学的にハッキリと判断しうる時に、人工呼吸器によって心臓を動かしつづけることは、かえって「死者の尊厳を犯す非人間的な行為」となる。「死者は、死者に対する生者の執着心から解放された時はじめて、死者としての意味を持ち、死者はうかばれる」のである。勿論、人間は社会的存在であるから、人の死というものは、ただ医者の意見だけで決まるものではない。そこには、人々による「死の受け入れ」ということがある。しかし、「死を受け入れる」ということは、誰もが勝手に自分の意見で、あるいは、相談しあって、人の死を決めるということではなく、死を認定しうる専門知識を有し、その権限と責任とをもっている医者の判断に同意するということである。従って、いわゆる「社会的合意」というものも、医学的に死を認定しうる「医者の見解に社会が同意する」ということが、その筋道にならなければならない。 「個体の生命は取り替えがきかない。代行できない」ものである。しかし、個の生命はただ個の中にのみ納まるものではない。それは、生まれてきたものであり、また、生み行くものである。個の生命は自分を超えて行こうとする。「生命の大海の中に、あらゆる生きものの命はうかんでいる」のである。そういう事に深く目覚めることが宗教心であろう。そのような自覚から、他の人への愛、別な人の生命に対する尊敬が生まれてくる。そしてまたそこから、自分の一部である臓器を提供しようという考えが出てくることは可能であるし、そのことは「決して人間の尊厳を犯すことにはならない」。仏教には五蘊皆空という考えがある。それは、「私という個体を構成しているものは何一つ私の所有物ではない」、「私の身命の所有権は私にはない」ということであろう。この立場に立てば、「私の臓器とか他人の臓器とかという考えは、おかしいのではないか」。 「放っておけば死んでしまう人の生命を救うことに智恵をしぼるのは、宗教家の仕事ではない。これは医者がやることです。50年であろうが60年であろうが、その生物的生命の中で本当の生命に会う、つまり仏法に会うということへ人々を導く、それが宗教家のやることだと思います」。 (また、先生は、脳死や臓器移植という我々が現在直面している問題は、過去の経典の字句の中にその答を見いだし得る問題ではなくて、仏教者として生きている現在の我々が、これを一つの縁として、仏教を本当に生きた教えになさねばならない、そういう機縁の問題であると述べられた。) 〈奈倉先生〉のご意見は「患者を客観的に見る医療から、患者の主体性を尊重する医療への転換」、「患者を生きる主体として、生かされて生きる主体として見る視点」が現代の医療の現場には大事なことであり、また、「私たち宗教者は、生命の主体的な意味を尊重する生命観に立たなければならない」というものであった。そのような観点から、「技術が発達すればするほど、医療における仏教者の役割は増大する」という考えを示された。 先生は、先ず、1)「脳死を死とみてよいのか」という項目を掲げて、脳死というものは、「体細胞の大部分が生命活動を営んでいても、死が確実に予想される段階で、それを一種の死とみなす」、そういう「臨床概念」であると述べられた。すなわち、先生は、大峰先生のように脳死を「死」と言われず、「死が確実に予想される段階」と言われたわけで、ここに、両先生の脳死に対する考え方の基本的な違いがある。 「なぜ脳死という概念を設定するのか」として、 1「脳死が死と認められれば、生きた人から臓器を取り出すことが可能になる」 2「脳死と判定された人への医療の打ち切りが可能となる」 という二点をあげて、これらは、いずれも「功利的立場からの期待」であり、このように「死をコントロ-ルすることによって、臨終を自然に迎えることが犠牲にされる」ことへの懸念を示された。そして、人の死は、本人の生命活動の終焉であるというだけでなく、本人と本人にかかわる人々との関係の変換であって、この変換が人々に受容されたとき死の過程は完了する。そのような「死の受容」において、従来からの死の三徴候や、体が「だんだん冷たくなり顔色が変って行く」こと、それに、看取り、通夜、葬儀、中陰などの習慣は重要な意味をもっている、ということを指摘された。 次いで、2)「臓器移植問題と生命観」という項目のもとに、 a.「医療の実践から得た生命観」として、
また、b.「移植医療の特徴と患者の課題」として、移植医療というものは、一つの生命体の「自然回復力」を基礎にした従来の「治す医療」とはその「医療の原理が異なる」ものであり、「他人の臓器を移し入れて患者のいのちの営み方を変えて行こう」とする「延命の医療」であるということを指摘された上で、「現在の移植医療の実体」としては、拒絶反応をおさえるために投与される薬によって他の病原菌や癌に対する抵抗力も減退せざるをえないから、この医療を受ける人には、「危険をかかえながら生きる」という心構えが必要であると共に、長い時間がたつと「再移植」が必要であり、この医療はどこまでも、「治す医療ではなく延命をはかる医療」であると説かれた。 最後に、3)「もし移植医療が頻繁におこなわれたとき生ずる問題と仏教者の役割」という項目をかかげて、
以上の如く、脳死および臓器移植というものを積極的に認めて行こうとされる大峰先生と、そういう医療の展開を止むなき趨勢としながらも、その現状に種々の問題があることを指摘される奈倉先生と、ニュアンスの異なる二つの意見を拝聴したわけであるが、両者に共通していたのは、今こそ、「本当の生命」・「生の根源的価値」への目覚めが必要であり、この事に対して仏教および僧侶の果たすべき役割と責任は重いということであった。この二つの意見を拝聴した後、禅文化研究所所長・理事長である平田精耕老師をお招きして、脳死および臓器移植という医学の現状をどのように見ておられるのか、忌憚のないところをお聞かせ願うことにした。 〈平田老師〉は1985年にロ-マ法王庁が出した「脳死は人の死である」という見解を踏まえ、生体学上の「死の判断、個体死の判断というものは医学に任せる」より仕方がない。ただし、人を「個体」として、すなわち、「人間の生命を一個の物質みたいに考えているところ」、更に言えば、「生命」という物質に基礎をおいた概念で「人のいのち」を捉えているところに根本的な問題がある。禅語には生命という言葉はなく、「法身の慧命」、「性命」、「仏性の命」と言われている。「仏の御いのち、あるいは慧命、そういう言葉でもって人間のいのちというものを捉えねばならないし、私は、それが仏教から見た本当の生命観だろうと思う」と述べられた。そして、脳死とか臓器移植という問題も、それが良いとか悪いとかというレベル、一々の事柄の現象面だけで捉えるのではなくて、そういう問題が出てくる背景ないし基礎のところ、すなわち、近代科学・技術と倫理ないし宗教というグロ-バルな視野、最も基本的なところで捉えて、その統一をはかるという方向を持たないかぎり、根本的な解決は得られないであろうという見解を提示された。 まず、大峰・奈倉両先生の意見に対して、「大峰さんの議論のように五蘊皆空説の立場に立つと、一つ間違えば虚無主義に陥ってしまう」ことを警戒せねばならぬし、また、奈倉さんのように「縁起説を金科玉条のように考えてしまうと、また偏ってしまう恐れがないわけではない」と言われ、有無の二辺を一刀両断した「理事無礙法界の世界」を摸索する必要があるとの立場が示された。かかる立場から、仏教は死を問題にしているからといって、医学界が「脳死を死と認めろ」とか、「脳死をどう思いますか」と、まるで免罪符をえようとするかのように、質問してくること自体が間違いである。「そういうことを問いかけている自分というものは何者であるのか、ということを問うているのが仏教である」と言われて、現在の医学界の態度に対する疑念を呈すると共に、翻って、仏教学界などが示した経典の字句解釈に基づく諸意見に対しては、大峰先生の見識を高く評価して、「経典の中にそんな論拠を探っても現代に意味をもたないと。確かにそうだと思う」と言われて、死句の立場(経典の言葉を皮相的に理解し、生きたはたらきのない立場)を批判された。 次いで、「慧命」ということを強調された後に、「医学の世界でも脳死と臓器移植について賛否両論に分かれて色々と難しい医学的な議論がなされているが、我々が言い得ることは、その結論のところを素人にも分かるように、且つ正直に、情報提供してほしいということだ」という医学界に対する提言を述べると共に、「脳死は法律的に容認されるようになってくるだろうと思います。それは致し方のないこと」であるが、「やはり、そういう情報提供がハッキリしない限りは、私個人としては、脳死そして心臓移植について、根本的には容認できないという立場を、今はまだ堅持しているのです」と言われ、正直な医学上の情報提供によって初めて、「社会的な合意というものが成り立つであろう」との見通しを述べられた。 最後に、「奈倉さんは非常にいいことを言われた。人間の欲望を人間の技術は満たすことが出来ないと。そうだと思います」と言われて、近代科学が我々に投げ掛けている問題の深刻さと、「現代社会において、科学・技術と倫理ないし宗教をどのように統一するか」が根本的な問題であることを指摘された。すなわち、かかる統一は、昔から問題とはなっていた。例えば、孔子の弟子の子貢のエピソ-ドとして有名な、「機械ある者は必ず機事あり、機事ある者は必ず機心あり、機心胸中に存すれば則ち純白備わらず」という荘子『天地篇』の言葉も、そういう問題を示している。従来、この統一は、例えば、宋応星の『天工開物』にみられる、天工にしたがって人工は働いて行くものだという天工優位説、また、方以智の「上道下器」の説にみられる天人合一の考え、さらには、わが国の佐久間象山にみられるように、西洋の技術を高く評価しながらも、それは東洋の道徳、つまり「天の道」に従って行なわれるものとする考え方、これらにおいては、すべて、天道という事において統一がはかられていた。しかし、科学・技術が発達した現代の社会においては、かかる統一はもはやはかりようがない。もう一度根本から科学技術と道徳ないし宗教との関係が考えなおされ、両者の統一が新たに構築されなければならない。このように説かれて、「現代科学を認めないわけではないけれども、だからと言って、何でもやれとは言えない」と言われ、「臓器移植を法律化するということですけども、法律に従って臓器を渡すとなれば、それは布施行・利他行にもならない。臓器移植は各人の意思に任せるということで移植を認める、現状ではそういうことしかないのではないかと思う」と結ばれた。 それぞれ立場を異にされる三人のご意見を拝聴して、研究会は、先にかかげた研究会の三方針、すなわち、
1)「答申」についての意見
|